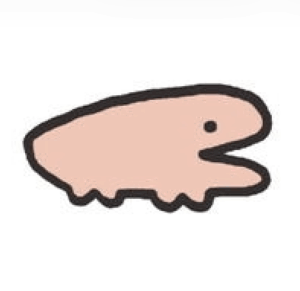矢野南小学校とサクラサクさんと行っている、「やのみープロジェクト」の第2回目が 1/16 に行われました。第1回では、余っている机と椅子を小学生とともに解体しました(下記URL参照)。第2回では、解体した家具の部材をあらかじめ製作した土台に釘やビスで固定し、作品制作を進めました。
(第1回:矢野南小学校で家具の解体ワークショップ/We Disassembled the furniture with elementary school students.)
今回は、小学生40人が6つの班に分かれ、前回同様に家具の解体を進めるグループ、土台に部材を貼り付けるグループ、制作する文字のデザインを行うグループに分かれて作業を行いました。ある程度解体と部材の固定を行った後は、小学生がそれぞれ自分の好きな作業を行っている様子が見られ、ワークショップを楽しんでいるようでとても嬉しかったです!

はじめはただの円形だった土台に、小学生がたくさんの部材を固定していき、授業が終わる頃にはとても迫力のある素敵な作品になりました。小学生が、普段は使用することのないインパクトドライバーや、エア釘打機などをプロに教わりながら楽しそうに使っている姿が印象的でした!


最後にデザイン班が作品の名称を考え、小学生による投票の結果、作品の名称は「時空の年輪」となりました!作品の制作はこれからさらに、大学生とサクラサクさんで進めていき、授業の最終回となる第3回目で完成する予定です!完成が楽しみです!

The second session of the “Yanomi Project,” conducted with Yano Minami Elementary School and Sakura Saku, took place on January 16th. During the first session, we dismantled surplus desks and chairs together with the elementary school students. In the second session, we progressed with creating artwork by securing the dismantled furniture parts to pre-made bases using nails and screws.
This time, approximately 40 elementary students were divided into six groups. Similar to the previous session, they worked in groups focused on dismantling furniture, attaching parts to the base, and designing the letters for the artwork. After some dismantling and securing of parts was completed, it was wonderful to see the students happily enjoying the workshop, each choosing their favorite task!
What started as a simple circular base transformed as the students attached numerous pieces. By the end of the session, it had become an impressive and beautiful piece. It was memorable seeing the students happily using tools they rarely get to handle, like impact drivers and pneumatic nailers, under professional guidance!
Finally, the design team proposed names for the piece, and after a vote by the elementary students, it was named “The Rings of Time and Space”! Production will now continue with the university students and Sakura Saku, with completion planned for the third and final session! We can’t wait to see the finished piece!
小林 / Kobayashi



.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)





.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
-1.jpeg)
.jpeg)
(大).jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)



.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)